三月。朝の通勤電車の混雑ぶりに変わりはなかった。分厚いコートが減った分だけ隙間に春が見え隠れしていた。都心部を横断する地下鉄の車内は、鉄の軋む悲鳴が固く掘り抜かれたトンネルに反響し、サラリーマンのうわ言のような荒い息遣いや、砕けたガラスが降り注いでくるような車内アナウンスの声によって、自然界ではあり得ない平衡を保っていた。だが、満員の通勤客や通学の子どもたちの平静さは上辺だけの装いに過ぎず、心の奥底で人々はパニックに陥っていた。
恵子も同じパニックを、ついに昨日から無言の裡に抱えていた。
恵子の降りる駅まであと二つ、というそのとき、くぐもった嫌な音が車内を走った。硬い何かを何本もいっぺんにへし折って、でもわずかにタイミングがそろっていないために音の輪郭がぼやけている、そんな鈍い音だった。ゼリーとグリースを柔らかい袋に詰めて毛布をかぶせた上から押しつぶして破裂させたような音だった。今年になってから何度も聴いた音だった。何度聴いても慣れることはなく、その都度背中から汗が吹き出し全身総毛立つほかない音だった。車内の誰もが同じ恐怖を隠し、音源の方角を見る者は皆無だった。
恵子は、自分が何をこらえているのかもわからないまま必死で何かをこらえ、ドアが閉まる寸前にいつもは通り過ぎるだけの駅へと降りた。階段を上り、改札口を走り抜け、サインを見つけてトイレに逃げ込んだ。洗面台に水を流し、震えている手指を濡らし、そして鏡を見た。そこに映る自分の姿は自分とは思えないほど美しく、またその美しさが恵子を打ちのめした。
恵子は、真新しいスプリングコートを着ていた。それはとても軽くて薄くて柔らかかった。明るく華やかな色々に満ちていて、春に飛びはじめたツバメの羽のような喜びにあふれていた。恵子は、肩に乗り背中を抱きしめそでを包み込み膝をくすぐるスプリングコートを全身に感じて湧きあがる幸福感に酔った。しかし、天空に舞い上がらんばかりの幸福感の裏側には、昨日までは知らなかった黄金色の地獄がはっきりと見えていた。
指先が何かに触った。目を落とすと洗面台の排水口から蔓草が伸びていた。壁をつたい、天井を這う蔓草が甘い香りのする花を咲かせていた。
蔓草の葉にはねた水滴が鏡に飛んで、そこから蝶が転がり出てきた。蝶は細かな鱗粉をきらめかせながら恵子のスプリングコートや花の間を遊ぶように飛んでいた。換気扇の音が高まったと思うとそれはハチドリの羽音だった。ハチドリは薄暗い蛍光灯に照らされてくるくると色を変えながら恵子の顔面に向かって羽ばたいていた。排水口から湧きのぼった蔓草ははげて色あせたピンクの塗り壁を濃い緑に覆い尽くしてしまった。蔓草から吹きこぼれた葉は濡れたようにふちを光らせていた。
開いた瞳孔の奥から網膜が反射し、乾いた口蓋にはりついていた舌が小さな音をたてて剥がれ落ちて前歯に止まった。
その軽い衝撃をきっかけにして、恵子は笑った。
それは満たされる欲望の原始林だった。恵子は自分の体中から立ちのぼる興奮と歓喜の匂いを嗅いでさらに高く舞いあがっていった。光る葉の隙間に覗く鏡に映る自分は、原始の花の美しさだった。
だが、言葉にも思考にもならない腐乱した感情の爆発には影があった。その影は歓喜の内側で恵子を埋め尽くしていた。昨日までの恵子はその影を恐怖と呼んでいただろう。しかし今朝、このスプリングコートを着た瞬間から影は恐怖の名を超えて恵子を飲み込んだのだ。
恵子の掌はスプリングコートのそでを滑り、さするように何度も上下してその実感を食い尽そうとするかのようだった。掌の下で体は冷たく、硬く引き攣っていた。
そのときまた、あの音がした。
地下鉄駅の汚いトイレに展開されていた原始の舞台は唐突に消えてしまった。
奥に並ぶ小部屋のひとつから、音は聴こえた。
痛む筋肉をむりやりひっぱって首をねじり、音のした小部屋を見つめていると、足元に血があふれてきた。ゆっくりと床を黒に近い赤色に染めてゆく血は、恵子のブーツに当たってわずかに盛りあがり、左右に分かれていった。
恵子は、ぬらつく床にすべりそうになりながらその小部屋のドアに手をかけた。恵子は泣いていた。泣きながらドアに手をかけて、叫びながらドアを開いた。恵子はそこに自分の姿を見た。
便器に投げ捨てられたように一着のスプリングコートがぐしゃりとなっていた。血を吸って元の色や柄は想像できないほど黒ずんでいた。襟元からは白っぽい紐のようなものが伸びて、タンクの向こうへ消えていた。その先の、影になっている隅に転がっている黒い毛玉のようなスイカ大の塊は、人間の頭部に違いなかった。しぼった雑巾のように細くねじれた袖口から、女の手首から先がぶら下がっていた。その指に奇麗な指輪はまだしっかりとはまっていた。だが胴体はもともと入っていなかったとしか思えないほど、薄っぺらかった。
このスプリングコートの主はたった今、自分のスプリングコートに潰されたのだ。持ち主の血を吸ったコートは満足そうに少しずつしわを伸ばし、ふくらみを取り戻し始めていた。早く次に着てくれる人間を見つけたいのだろう、昨日の恵子のような女を。
恵子は後じさった。
自分の着ているコートが、動いた。動いたように感じられた。だから、後じさった。気のせいか。いや、そうではない気のせいではない。恵子にはわかっていた。始めからわかっていたのだ。わかっていてなお魅入られたのだから、こうなることはこのスプリングコートを買った瞬間からわかっていたのだ。
肘や脇の下のあたりがもうすでに窮屈になっていた。裾も絡まり、歩くにももたつくほどだった。恵子は洗面台まで辿りつき、もう一度鏡を見た。
美しかったコートの形は崩れ去り、あんなに柔らかそうだった布地は岩のように鈍く光り、血管を圧迫された顔面と手の色がどす黒く変わり始めていた。コートに締めつけられてゆく体の苦しみはかつて経験したことのない歓喜の熱となり、下腹部の奥から悦楽の震えが背骨をつたって喉へ到達した瞬間、恵子は体を大きく反らせて最後の声を漏らした。
(完)



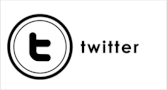

コメントをお書きください
oretasakana (金曜日, 16 12月 2011 02:13)
小説を書きたい欲望は、いまでもふつふつとあぶくを立てている。だが、私のノートには書きかけの断片が無数に転がっているだけ。数少ない完成した作品のひとつが、これ。科白もなければ登場人物もひとりだけ。