クマは不眠症に悩んでいた。
冬がくるまでに治さないと死んでしまうかもしれない。眠れないクマに症状の名前を教えたフクロウはいらぬことを付け加えてクマをおどかしてしまった。クマは眠らなきゃ治さなきゃ死んじゃう死んじゃうと焦燥感に駆られてますます眠れず、森中を歩き回った。
この森にはたくさんの動物たちが暮らしていた。クマは動物たちを順に訪ねた。フクロウ、シカ、ハリネズミ、ヤマネ、イノシシ、ノブタ、ツグミ・・・。彼らのすみかで一晩一緒に眠らせてもらうためだ。みんなの眠り方を教えてもらって真似してみたのだ。
でも、やっぱり眠れない。
「残念だなあ。いつでもまたおいでよ」
みんなそう言ってくれた。
あるとき、首輪をつけた灰色の縞模様をした猫に出会った。森を出て少し歩くと村があるのだが、その村の外れの森に一番近いところにある農家の猫が遠出の散歩をしていたのだ。ぼくはラムジーだよ、きみは? と猫のラムジーは聞いたが森のクマには名前がなかった。ぼくはクマさ、と答えるとラムジーは笑って、よろしくねクマ君と言った。
「へえ、君は村に住んでるんだね」
「おいでよ、みせたげるから」
ラムジーは森の端にある村を見下ろす高台にクマを案内した。
「あの、一番手前に見える茶色い屋根に青い壁が僕んちだよ」
クマは高台にある自分と同じくらい大きな岩影からそっとラムジーの家とラムジーの村の光景を眺めていた。
「この岩より向こうへは行かないほうがいいって、フクロウさんに言われてるんだ。危ないからって」
「ふーん、そうなんだ」
ラムジーは岩の上にのぼって顔を洗ったり耳をかいたりしていた。日だまりに座って動かぬ岩はじんわりと暖かかった。ラムジーはあくびをして、クマ君僕眠くなっちゃったよと言い、岩の向こう側へぽんと飛び降りてまた遊びにくるねと手を振って帰っていった。
クマは帰っていくラムジーの後ろ姿を見送っていた。小さな体が草に隠れ、草が倒されて影になり、影がゆらゆらと伸びていくのを眺めていた。やがて農家の敷地にふたたびラムジーの灰色が見えた。ラムジーは青い壁の母屋のとなりにある焦げ茶の板壁の納屋の脇、薪が積み上げてある上にひょいっと飛び乗って、ちょうどぴったりのくぼみにはまり込んでまん丸くなってしまった。
クマはそれ以来、毎日高台へやってきて、ラムジーの家を眺めていた。いつ見ても、ラムジーは薪の上ですやすやと眠っているのだった。太陽が傾いて納屋が山の影に飲み込まれる前にちゃんと猫は目を覚まして家の中へと消えていく。きっと中には薪の上と同じくらい暖かくて居心地のいい寝床があるんだろうな。クマはそう思った。
ラムジーがまた森へ遊びにきた。
「やっぱり遠いからさ、あんまり来れないんだよ。それにちょっぴり怖いし」
「怖くなんかないよ。森のみんなはやさしいよ。みんなね、僕に眠り方を教えてくれたりもしたんだよ。まあ、うまくはいかなかったんだけどさ」
「ええ? クマ君は眠り方がわかんないの?」
「うん、不眠症なんだって」
クマは自分の悩みを猫に話した。そして、ラムジーがいつも気持ち良さそうに眠っているのを見ていてうらやましい、と言った。
「そうかあ。じゃあさ、今度は僕の眠り方を試してみない?」
ラムジーの家の主人は市場へ出かけていて今日は留守にしている。太陽も暖かく照っている。クマは猫に連れられて森を出て村はずれの家へ向かった。
森を出て草の丈も低くなると、クマは自分の大きな体がすごく目立っているのではないかと不安になった。
「ラムジー、大丈夫? 僕、見つからないかなあ」
「大丈夫さ。今日は家の人みんないないし、僕んちは村の一番奥のほうだから」
ラムジーは大きなクマの顔を見上げながら走っていたが、追いかけるクマはゆっくり歩いているだけだった。やはり大きい、ラムジーは言葉とは裏腹に森の外で見るクマの偉容に今更ながら驚愕していた。
クマがいつも高台から眺めていたラムジーの家に到着した。遠くから見ていたよりもずっと小さくて、すごく鮮やかで、とても暖かい場所だった。ラムジーはさっそく納屋の脇へとクマを案内する。いつもの場所に猫は納まり、クマは薪の山に寄りかかるように寝そべってみた。
「いいかいクマ君、まあるくなってごらん。ふわふわ浮かぶシャボン玉になったつもりでさ、まあるく、まああるく・・・」
そう教えてくれたラムジーは、すぐに眠り始めてしまった。
クマは、ラムジーが教えてくれたとおり、シャボン玉のようにふわふわとまあるくなって、ついには顔をおなかにうずめて本当に大きな玉のようになってしまった。
暖かな日差し。
乾いた薪の匂い。
森の中とは違う、吹き渡る風が木の葉をくすぐる音。
高く響く鳥の声。
ぶるるる、ぶるるるるという小さな振動。
それは、ラムジーが喉を鳴らしている音が薪を通して伝わってくるものだった。ああ、なんて気持ちがいいんだろう。クマはぶるるるに溶けてしまいたいと感じていた。
いつしか、クマは眠っていた。
そろそろ日が陰るころ、ラムジーはちゃんと目を覚ます。
「クマ君、もう起きようよ。家の人、帰ってきちゃうよ」
しかし、クマは起きない。
なにしろ、春から夏、秋深まる今日に至るまでずっと眠れなかったのだからあたりまえである。
「クマ君起きてよ。起きて森へお帰りよ。家の人に見つかったら大騒ぎになっちゃうよ家の裏にクマが寝てたら。ねえ、クマ君たらあ」
猫は小さな手と細い爪でクマの体をカリカリとかじってみるのだが、クマは起きない。
「こまったなあ。眠れたのはよかったけど、今度は起きられないんじゃあ・・・。あ! 帰ってきちゃった大変だ!」
猫はとりあえず、物陰に隠れた。クマのそばに自分がいたのでは、むしろ家の主人を刺激してしまう。それなりにかわいがられているのを自覚していたラムジーは、自分を守るために必要以上の勇気を主人が発揮してしまうかもしれないと危惧したのだ。
「うわああああ! クマだ! クマがいるううう!」
「きゃああ! 大変! あなた早くなんとかして!」
「なんとかって言ったっておまえ、あんな大きなクマ、お、大きな声出すな起こしちまったらどうすんだ大暴れするぞ。そうだよし、眠らせたまま捕まえよう」
「捕まえられるのあなた?」
「おまえは家の中にいろ、ラムジーはどこだ? ラーム! ラームジー!」
家の主人は村人を集めに戻った。奥さんはラムジーを探しに家の中へと消えた。ラムジーはもう、森へ向かって走り出していた。
森のみんなを呼んでこなきゃ。
村の人が集まってきたら、クマ君捕まって殺されちゃう。
ラムジーは森へ飛び込んで走り回りながら大声で叫び続けた。
「森のみんなー! 来てくれよー! クマ君が、クマ君があー!」
ラムジーの主人は、村人たちにそれぞれ大きな網や石弓やハンマーを持たせて、そろりそろりと戻ってきた。
「いいかみんな。あの奥の納屋のところにでっけえクマが寝てるんだ。起こさないようにそおっと網をかぶせるんだ。網をかぶせてからいっせいに石弓で撃つんだ。気をつけろよ。息を合わせろよ」
汗をだらだら流して震えながらも、村人たちは歯を食いしばってうなづいて、ゆっくりと納屋の方へ回り込んだ。
が、そこには・・・。
フクロウ、ヘラジカ、ハリネズミ、イノシシ、イタチ、ちゃんと起きているクマ・・・。
森中の動物たちが、眠っているクマのまわりに立ちはだかっていたのだ。
村人たちは驚いて一目散に退却した。
「なんだっていうんだ」
「あ、あんなたくさんの動物が集まってるとこなんて見たことない」
「あれじゃあ手も足も出ない」
「か、帰らせてくれ」
「どうすりゃいい、どうするんだ」
「どうするもなにも・・・」
村人たちはなす術もなく、ともかくも順番で見張りを立てることにした。覗いていると、動物たちは身動きもしない。ときおり、一羽あるいは一頭一匹が音もなく動物の山から抜け出ていく。しかしその瞬間別の動物が空いた隙間や穴をさっと埋める。動物たちもまた、交代でクマを守ろうと毅然たる態度でそこにいた。そうして夜が更けた。動物と人間の、にらみ合いというほどには敵意のない、しかしそれぞれに緊張と不安が入り交じった静かな対決は一晩中続いた。
山の端から曙光が差し込んだ。冷たかった夜明けの風が暖められ、ほっとしたようにフクロウが大きく羽ばたいた。納屋のまわりも日が差し始めて明るくなった。光が眠るクマの顔をなでたとき、まぶしさにクマが目覚めた。
「あーよく寝たなあ。ラムジー気持ちいいよう。こんなにぐっすり眠ったのは本当に久しぶりだよう。ラムジーのおかげだよう。・・・あれ? みんなどうしたの?」
フクロウが答えた。
「やあ、クマよ、よかったな。ゆっくり眠れたようじゃないか。だがね、ちょっと今、大変なことになっているのだよ」
イノシシが耳元で囁いた。
「いいですかクマさん、これから森へ帰るんです。そのまま立ち上がらないで、わたしらの影に隠れたまま、森の方へ向かってください」
フクロウの合図で動物たちがいっせいに動き出し、見張りの村人は腰を抜かしてしまい仲間を呼びにいくこともできない。動物たちのかたまりは、ゆっくりと森へ消えていった。
村人たちはあっけにとられ、口々に不思議がっていた。
「手品みたいだった」
「クマなんか最初からいなかったみたいだった」
「いったいどういうことなんだろうねえ」
「まあなんにせよ、何事もなくてよかったさ」
「おう、よかったよかった」
ラムジーは離れた屋根の上から、一部始終を見守っていた。
森に今年初めての雪が降った日の朝、ラムジーがやってきた。
「おやラムジー君。あのときはクマを助けてくれて、ほんとうにありがとうなあ」
「フクロウさん、こんにちわ。僕のほうこそ心配していたんです。僕のせいであんな大騒ぎになっちゃって、クマ君や森のみんながひどい目にあったらどうしようって」
「そんな心配は無用じゃよ。それよりもクマの不眠症は森の誰一人治せなかったんじゃ。それをラムジー君は、治してくれた。わたしからも礼を言うよ」
ラムジーはにっこり笑って森の奥へと走った。森の奥、クマの新しい寝床のそばで、猫とクマは再会した。
「あ、ラムジー!」
「あ、クマ君」
ラムジーとクマは高台の大きな岩に並んで座った。二人の目の前に広がる草原や村や遠くの山並みはところどころうっすらと白い。
「もうすぐ冬だね」とラムジー。
「もう冬だよ」とクマ。
「そうだね、お尻がつめたいや」
「ふふ、僕のお尻は分厚いからなあ」
「僕もよく眠るんだけど、クマ君の冬眠にはかなわないよ」
「ラムジーの昼寝を一年分足し合わせたら、きっとおんなじくらいだよ」
「ははは、そうかもね」
ラムジーは森の友達に会えなくなるのが急に寂しくなった。
「そんな顔しないでよ。春になったらまた遊びにきてよ」
「春って、いつ頃?」
「この高台、君んちからでも見えるだろ? この大きな岩を覚えておいて。この岩が雪に覆われたら、僕は冬眠するんだ。目が覚めると、この岩は雪から姿を見せるようになってる。だから、この岩の分だけ雪が溶けたら、僕はもう目覚めているはずさ」
「わかったよ。この岩を君だと思えばいいんだね!」
「そうだよ」
「じゃあ、岩が雪から姿を見せる頃にまたくるよ」
「楽しみにしてるよ」
「おやすみね、クマ君」
「おやすみ、ラムジー」
その冬ラムジーは高台の見える窓辺に新しい寝床を作ってもらい、毎日毎日眠っては高台を眺め、雪に隠れた岩を探しては眠り、大きな体の岩が姿を現す日を待ち続けたのである。
(完)



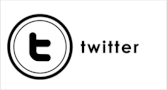

コメントをお書きください
oretasakana (火曜日, 20 12月 2011 21:55)
これまでのところ、最長作品か。これは童話である。動物が大好きな大人のための童話である。そうやってくくると、ありふれているなあ。でも、私は感動した。