地下に孕まれる真珠
指のきれいな女だった。
色の褪せた黒のデニムを履き、やはり真っ黒なナイロンのハーフコートを着込んでいて、セーターとキルティングが重なっていてまるでタイヤメーカーのマスコットの影のようだったが、狂ったように指のきれいな女だった。
襟元までファスナーを閉じていたのは記録を更新し続けた暖冬が突然消え失せて冷たい冬本来の空気が戻ってきたせいだろうが、夜の地下鉄車内は暖房と人いきれでむしろ暑い。そのせいで彼女の黒い前髪に半分かくれた顔は紅くほてり、滲んだ汗が額に光っていた。
それなのに、その指だけはまるで雲間から射す薄日のように白く輝いていて、深い森からのぞく夜更けの三日月のような弓なりを描き、死を招く女神の淫らで危険な誘惑をたたえていた。
なんだってこんな指があるのだろう。おそろしく美しい指から私は、視線を剥がせないでいた。視界の中心で絡み合った指だけが生きているようだった。
地下鉄は駅に到着するたびに疲れて気が立った乗客を吐き出してまた飲み込む。吐き出した先はまだ遠く、混み合っていた。混雑は車内のみならず、駅のプラットフォームも待つ人にあふれ、線路上では一〇両編成の電車が待たされ、信号待ちを繰り返しながらにじり進むようだった。幾重にも折り重なるように包み覆う圧迫感と、モーターのトルクとブレーキ、巨大なバネが生み出す前後左右上下の揺れが、乗客を押しつぶしていた。誰もが疲れて揺れていた。
その中心に、貝が胎内に真珠を育てるように、巨大な生き物のはらわたの奥深いここに、指が輝いていた。
(完)



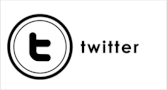

コメントをお書きください