二十一歳のアリス
あと二日で二十一歳になろうとしていたアリスは、二十一歳のアリスという美しい生き物として新しく生まれようとしていた。誕生日とはそういう日なのかもしれない。何年か前のその日に生まれたのではなく、その日にまた誕生する日なのかもしれない。
偶然の神秘を信じるか、無作為の乱数として処理してしまうか、健二にとってはそういう岐路に立たされた一日だった。なんでもない平均値的朝は瞬く間に打ち壊され、見たこともないほど急峻な崖に立たされていると気づいたときには戻れる道はもうなかったのだ。
バイト故の単調で極めて安易な次元に属する割り当てられた仕事、食器洗浄機の世話をする係を務めていた健二は、十五分の休憩の一回目に、アリスと五分間だけ狭い控え室で二人になった。
「・・・で、すっかり忘れてたの。でね、こないだ実家に帰ったらあたしの成績表が届いてるわけ。まあ、そう、だよね」
「大学としては、報告しとかないと、ってわけか」
「宛先もちゃんと父親になってたのよ」
「それじゃ開けて読むわな。でもさ、成人だよね? あれ、いくつだっけ?」
「こんど二十一になるの。あと二日で」
ここから後の会話が四分間あるのだが、健二は覚えていない。二日後にアリスが二十一の誕生日を迎える。その突然の情報がデータが、健二をおかしくしたのだ。
バイト先でたまに一緒になるだけの女の子。会うか会わないかは偶然次第だった。健二は、自分の人生に偶然以上の確からしさを欲望しなくなって久しかった。何かをなんとしても手に入れたいとか、確実を越えるほどの完全なる事前の保証を求めるとか、そういう欲を健二は捨てていた。それは、そういう欲を満たそうとする自分の醜さや、欲望が満たされたときに気づく失った何かの大切さ、いままでの恋愛沙汰やら競争社会での敗北と逃走劇で負った傷の痛みのせいだった。
だから、バイト先でたまたま会うより多くのアリスを求めてもいなかったのだ。でも、求めていないのでもなかった。むしろ健二はアリスをなによりもたくさん求めていた。健二にとってはしかし、アリスを求める思いとアリスに何かを求める思いとは次元を異にしていたのだ。かつて、好きになった女の子にあまりにも多くを求めたせいで彼女を苦しめただけの失敗に終わった恋愛があり、それから何年も経たある夜、突如健二は泣いたことがあったのだ。自分の愛情は誰も幸せにしなかったと、気づいたせいだった。それ以来、健二の愛は一切の物音を立てなくなった。
静かな愛情をアリスに抱いていた健二は、知ろうともしていなかったアリスの誕生日が二日後であること知り、その日を祝ってあげるべき恋人もたまたま暇な友人もいないと知った。二十一歳の誕生日の到来をアリスはほんの少し寂しげに健二に告げたのだ。
それから、あるメモの一葉をアリスに手渡すまでの四時間、健二の心臓は普段の倍のテンポで走り、全身の汗腺は汗を噴き出し続けていた。そのメモには、「もし今日のバイトが終わってからヒマだったら、ごはん食べないか? 誕生日のお祝いしようよ」と書かれていた。この文章を書き上げ、このメモを渡すまでの健二は、以下の様だった。
休憩が終わりアリスを残して厨房へ戻った健二は、相棒である食洗機のLED表示を見つめたままいったん動かなくなった。彼の停止は同僚に背中をつつかれ食器の交換を促されるまでの十分間続いた。マネージャに見とがめられなかったのは幸いだった。
普段の三分の二程度の遅さではあるものの、やるべき作業をぎりぎりでこなしつつ、健二はひたすら思考の小径を往復していた。アリスの二十一歳を祝いたい。自分はもう三十過ぎで、しかもバイトで食いつなぐ生活である。自分にとって誕生日など、カレンダーの六曜とおなじくらい、あっても見ないし気づきもしないようなものだった。でも、素晴らしくきれいで、輝くほどに息づく女の子の二十一歳は、特別だ。アリスの人生にとって、これほどまでに特別な日はないはずなのに、昨日と同じように過ぎ去ってしまい、何十年にも及ぶ時間の重石にいつか埋もれて消えてしまうかもしれないなんて。そんなこと、絶対だめだ、だめだだめだ。でも、自分が、この健二が、言ってみればこの悲劇からアリスを救い出すなんて、できるのか? できっこない。俺はバイト先でバイトしてる他のバイト君以外の何者でもないのだから。俺に誘われて嬉しいわけがない。嬉しいと思うと思う方がどうかしている。祝ってあげたいと思っているだけでいいじゃないか。いつもそうじゃないか。自分が求め、思うのは大切だし自由だ。でもそれを相手に伝えてしまうのは、人の心に土足で踏み込むに等しかったじゃないか。伝えたいと思うのは俺であって、伝えてほしいとアリスが思ってるわけじゃない。
ここまでは、よくいる「めんどくさい引っ込み思案な自己主張男」であった。だが、今日の健二はここからが違った。やはり、恋に目がくらんでいたのだ。目がくらんで、暴走した。
でも、やっぱり。
おれはどちらでも変わらない人生を送るだけだ。アリスの二十一歳の誕生日を、アリスと一緒に食事をしてお祝いをしてもしなくても。それは中間的可能性である「誘って断られたケース」でも同じことだ。だが、もし、もしもだ。アリスが、もし俺が誘ってお祝いをするのを受け入れてくれたならば、アリスの人生は絶対に違うものになるはずだ。二十一歳の誕生日を何事もなく過ごした女の子の人生と、誰でもないような俺であれ、誰かに祝ってもらった女の子の人生は、交換不能ではないか。俺はもちろんアリスの恋人ではないしその候補ですらない。最悪の表現をすれば友人ですらない。ただの知人だ。通りすがりに毛が生えた程度の俺。でも俺は、心からアリスの幸せを望んでいる。アリスの幸せがなんなのかなんてわかるはずもないが、なんであれ幸せを。
通りすがりに毛が生えた知人である俺は、アリスの幸せを望んでいて、二十一歳の誕生日について迷っていられる猶予はあと数時間しかない。明日になってからあさっての約束をとりつけるのは今日誘う以上に不可能なことだ。だって、次のバイトは来週だし、連絡先も知らない。それを聞くことこそ、絶対に自分ができないことだ。
ようやく、ひとつの決断ができた。誘ってみよう。
ただ、なんていおうか。断る自由が最大限に残されてないとまずい。断りにくくて、断りきれず、なんとなく応ずるほかなくなったアリスは見たくない。誘い方、言葉の選択が難しい。逆から考えてみよう。断りやすい断り方は? 「用事があるから」だろう。二日後の誕生日になんの予定もないことはさっき聞いてしまったが、今日については違う。俺はまだ今日の夜ヒマであることは知らない。ああ、先走っている。ヒマなのかどうか、俺とアリスは話題にしなかった、ということだ。だから、仮にヒマであったとしても「用事があるから」といえば済む状態なのだ。ということは、要点は一気に誘え、だ。ヒマかどうかを尋ねてからじゃなくて。「ヒマだったらお祝いの食事に」と、一気に全部さらしてしまえばいい。それなら、「気持ちはうれしいけど用事があるから、ありがとね」と断れるだろう。少し気が楽になってきたぞ。つまりそんな誘い文句なら誘ってもいいんだってことだ。じゃあ、実際のところなんて書けばいい? これもまた難題だ。
ここまできて健二は、あれから二回目の休憩に入った。控え室では他人の目があるので、健二は紙一枚と鉛筆を持ち出して店の裏へ出た。ビルの壁の滑らかな部分を見つけ、そこに紙を押し当てて考えに考え抜いて辿りついた結果の文章を書いたのだった。それがあのメモだった。
健二よりも一時間早くバイトが終わったアリスは、駅前にあるカフェまでどうやって来たのか、窓際に腰掛けて今ストローで飲んでいるものがいったいなんなのか、まったくわからないでいた。健二がやってくるまで、一時間ある。その間に平常心を取り戻さないと、とアリスは焦っていた。
昼間ここを通ったとき外から見たカフェの大きなガラスに街と自分が映り込んでいたのを思い出す。こうして内側から夜の顔つきになった街を眺めると、ガラスに映る自分の姿が重なっていた。虚と実のコントラストが今のアリスを象徴していた。
「そのまんまだわ」
アリスはつぶやいた。
こんなふうになるとはね。誕生日はいつもあきらめてたのに。今年だってそれでよかったのに。あの人たち、歩いてるのね。ああやって、足を踏みおろして。あたしの顔、体、半透明で浮いて、何処にも本当はいないみたいになってるの。健二さん、なんであんなこと言い出すんだろ。あたしもどうかしてる。用事があるっていえばいいのに。メモを読んだときの顔、見られちゃった。目が合っちゃったもの。交わす余裕ゼロだったわ。
アリスにとって、健二の誘いは空からカエルが降ってきたようなものだった。健二はどちらかと言えばもの静かで、バイト仲間でも年上だったせいか、一歩離れたところで一人立っている雰囲気があった。アリスは健二を意識したことなど一度もなかったし、それ以上に健二の視界にこそ自分は映っていないと思い込んでいた。
たしかにアリスは覚えていた。今日の控え室で退屈しのぎの相手をしてくれた健二に誕生日があさってだと話した瞬間、健二の様子が変わったような気がした。どこか上の空というか、なにか大事な忘れ物を思い出してしまったときのような顔で、それから生返事になったのだ。
ひょっとして、あれがそういう顔だったのかしら。誕生日のお祝いをしてやらなきゃいけないのだろうか、とかなんとか考え始めちゃったのかしら。
メモは言葉としてはともかく、まぎれもなくパーティへの招待状だった。それはアリスの目にうっすらとではあるが涙を浮かべさせ、文字をわずかながらぼやけさせた。しかし同時に、健二に無理をさせてしまった自分の責任も重くのしかかってきた。言わなくていいことを言ったせいで、聞かれもしなかった問いに答えたせいで、健二にすれば知りたくもなかったアリスの誕生日がいつであるかをその二日前という絶妙の時期に知らされてしまったせいで、あのつたない招待状を彼に書かせてしまったのだとしたら。
断るべきだったなあ。やっぱり。教えちゃったときに一度でしょ、誘いを受けちゃって二度。二度も続けて健二さんを困らせてるってことか。困ったなあ。どうしよう。
こうしてアリスもまた、見当外れのことをあれこれと考え悩んでいた。
健二は健二で、やはりアリスが断りきれなかっただけなのではないかと煮え切らないことをいつまでも考えていた。メモを読んだときのアリスの表情はびっくりもしていたが、喜んでいたようにも見えた。輝いていたように見えた。とはいえ、不安と緊張と遠慮から、ほとんどアリスの顔をまともに見られなかったので、そのあたりに自信はなかった。ああでもないこうでもないと、健二は彼の精神的能力のすべてをアリスについての思考に注ぎ込み、バイトを終えた。
この男女は、恋人同士ではない。明日、いや、今夜にもそうなるのかもしれなかったとしても、お互い好きでたまらないとか一方が他方に想い焦がれているとかでもなんでもないのだ。
しかし、そこに幸せの香りが漂っていた。駅前のカフェの大きなガラスには、うつむき加減のアリスの笑顔が映っていたし、バイト先から駅へと向かう道にはテンポの良い健二の足音が響いていたからだ。健二の書いたつたないメモの言葉には、健二の精一杯の愛情が込められていたし、アリスは健二の言葉を受け入れて、喜んでいたのだ。なにも要求しない、なにも失われない、愛が二人のあいだに了解されていた。二人にとって、こんなに幸せなことはなかった。
その夜、二人は数時間、一緒に過ごした。アリスはたくさん食べて、たくさんしゃべり、たくさん笑った。健二はたくさん飲み、たくさん聞き、やっぱりたくさん笑った。アリスはその後幸せな結婚をし、母となるのだが、毎年の誕生日を家族が祝うたびに、この日のことを少しだけ思い起こして、このときの幸せの香りをいとおしんでいた。
同じ頃、健二はアジアの小さな島を渡りながら貧乏生活を続け、やせて真っ黒に日焼けしていた。それでもアリスを思わぬ一日を過ごすことはなく、アリスにおやすみを言わずに眠る夜もなかった。二人は幸せだったのだ。
(健二の手紙)
アリスへ
俺も同じかそれ以上に幸せだったよ。アリスが楽しそうにしてたから。もちろん俺も楽しかったけど、そんなことはどうでもよかったくらい、幸せだった。
俺たちって、ほとんど他人だった。どこに住んでるのかも知らないし、俺が何歳かもアリス、知らないよね? 教えないけど。それでもさ、あの誕生日パーティのときみたいに、一緒にいられるのって、本当に幸せだと思ったよ。あの日の後もやっぱり俺たちはほとんど他人のままだったけど、それでいいんだ。なにも変えないけど絶対なくならないような、そういう幸せを俺は感じられたから。
そうそう、俺は今タイにいます。あるじいさんから壊れた屋台をもらって、修理してまずいソバ屋をやりながら街道で暮らしてる。タイの人はまずくても笑って食べてくれるから優しいよ。
アリスももうすぐ卒業じゃないか。おめでとう。これもまた少し早いお祝いになっちゃうけど、その日にそこに居られはしないから、今、ここで。
アリスはとてもきれいな女の子です。どうか、幸せに生きてください。幸せになってくれれば、俺も幸せです。
あなたの健二より
(アリスの手紙)
健二さん
やっぱり大人は大変です。あっという間に一年が経っちゃったなんて。新入社員は毎日がイベントだらけで、いつも誰かに世話をされて、自分の時間もペースもないのね。健二さんはこういうのがきっと苦手だったのかしら。
卒業式、お花届きました。ありがとう。信じられなかった。しかもタイだと思ってたのに、カンボジア? 道理で、タイにいないわけです。わたしね、卒業旅行にタイへ行ったのよ!
一緒に行く友達を必死で説得して、安くてきれいなところがいっぱいあるからって言って、健二さんがいると思ってたタイに無理やり連れてったの。
あの日みたいに、とても優しい偶然がわたしたちをまた会わせてくれないかしらって、ずっとお願いしてたんだけど、だめだったわ。カンボジアに行っちゃった後だったのね。まずいソバ屋さんの屋台、ずいぶん探したのよ。
健二さん、ありがとうね。私は幸せでした。健二さんのおかげで、きっとわたしは大丈夫な気がする。幸せの香りを教えてもらったから。
それより、健二さんの方がよっぽど心配。だって・・・。言わなくってもわかるわよね。
でも、きっと、健二さんも大丈夫なのね。とっても弱そうなくせに、実は強い人だから。
またいつか、何処からでもいいから、お手紙ください。
大人になったアリスより
(完)



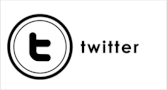

コメントをお書きください